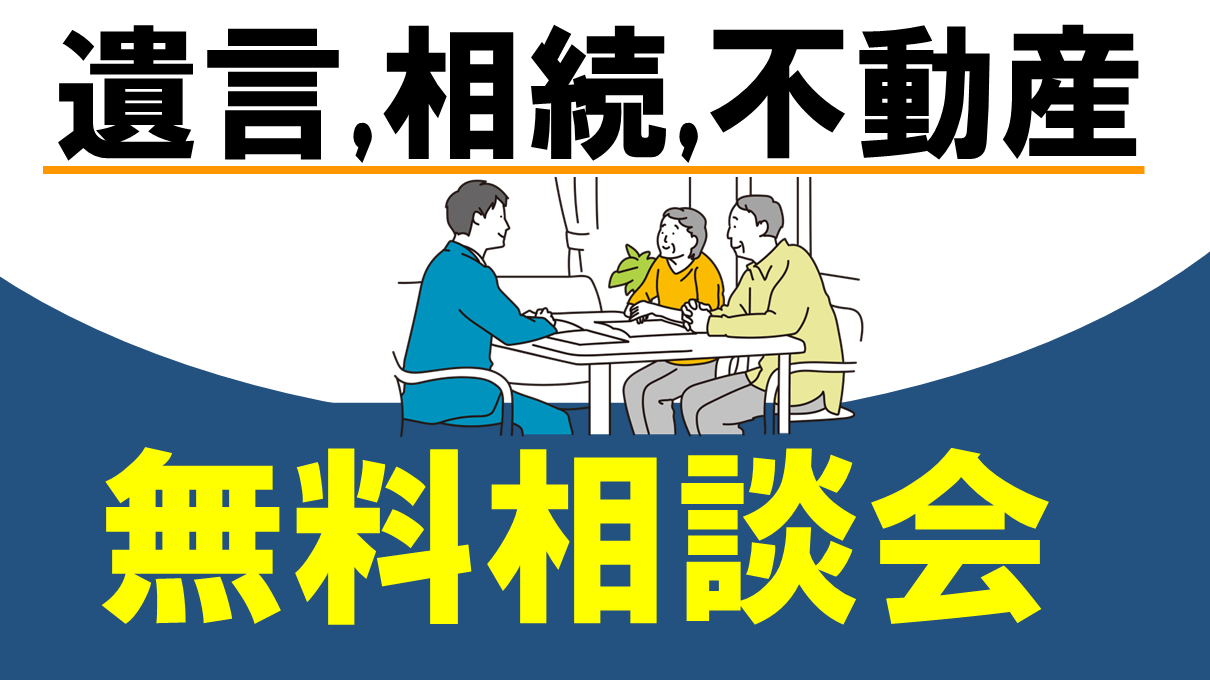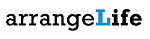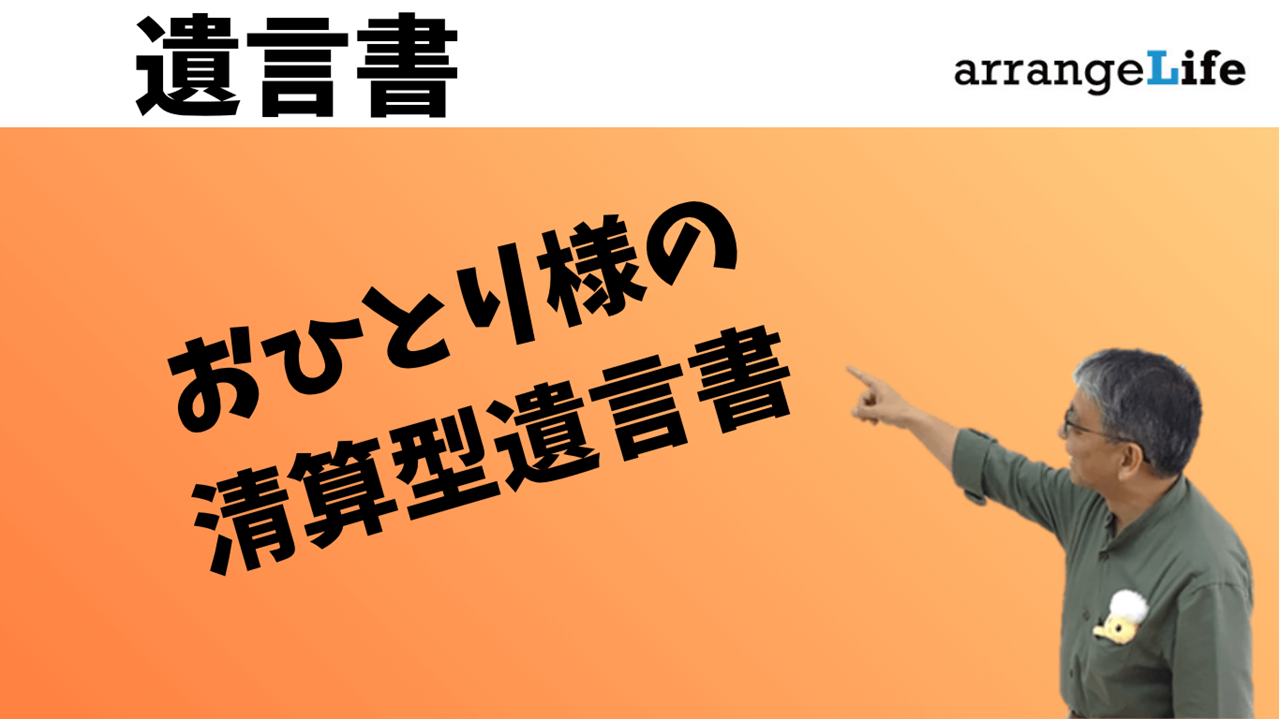おひとりさまが作る遺言書でよくある「清算型遺言」を遺言相続専門の行政書士が解説します。
著者:行政書士 正木隆雄 埼玉県行政書士会朝霞支部(朝霞市、新座市、志木市、和光市)所属
遺言、相続、終活を専門とし、不動産会社も経営しながら、地域密着でシニアの暮らしの支援を行っています。
清算型遺言とは?
おひとり様(独身・子どもがおらず相続人が少ない等)の中には、保有する不動産を兄弟姉妹や甥姪に承継させるというよりも「売却して現金化し、寄付・遺贈したい」という意思を持たれている方も少なくありません。
そのような場面で用いられる遺言形式が、いわゆる 清算型遺贈(清算型遺言) です。
例えば「私が所有する土地・建物を死亡後売却し、その売却代金から諸費用・債務を差し引いた残金を〇〇団体に寄付する」といった内容の遺言を作成しておくことで、管理が大変な不動産を後続に残さず、現金で整理・寄付できるメリットがあります。
しかしながら、この方式には「不動産を売却する手続」「税務」「登記」「遺言執行者の選任」など、注意すべきことが多くあります。以下、ポイント・注意点を整理していきます。
清算型遺言で注意すべきポイント
特に注意すべき点を整理します。おひとり様であっても、これらを押さえておかないと遺言の実行が滞ったり、受遺者・相続人・寄付先とのトラブルになったりします。
① 遺言執行者の選任
清算型遺言は、不動産売却・債務支払い・登記・分売・税務申告など多岐の手続を伴います。不動産の売却が必要なため、相続人・受遺者・寄付先との調整も必要となります。また、遺言執行者(遺言の通り実行する人)の指定がないと、相続人全員の同意が必要になる場合もありますので、遺言書の中で「○○を遺言執行者とする」と明記した方がスムーズです。可能であれば、相続と不動産売却に詳しい行政書士など専門家を指定しておくと安心です。
② 登記・名義変更の流れ
不動産を売却する前提であっても、登記手続は省略できません。特に注意したいのが、直接被相続人(遺言者)から売主への移転登記は原則としてできず、まず相続人名義に登記を行った後、売買契約・所有権移転登記を行うという流れが一般的です。
つまり、清算型遺言の形で「不動産を売却」と記載してあっても、相続人全員による共有登記→売却という登記上の流れを踏む必要があります。なお、遺言執行者が選任されていれば、この登記は遺言執行者がおこないますので相続人の協力(署名押印など)は必要ありません。
③ 不動産売却・換価処分の可否・時期
不動産を売却して換価するという点が清算型遺言の特徴ですが、売れるかどうか、売れるまでにどれくらい時間がかかるか、売却費用・税金(譲渡所得税など)はどの程度かをあらかじめ検討しておく必要があります。
例えば、売れにくい土地(山林・田畑・遠隔地・崖地・再建築不可物件など)を対象にしてしまった場合、売却が進まず遺言の目的達成が長期化するケースもあります。
売買契約が終わったあとは、契約条件(測量、建物解体など)を行っていきますが、ここでも遺言書に事細かく記載していないと実務上では不都合が生じます(解体して更地にしたあと建物滅失登記ができないなど)。清算型遺言の作成時に、不動産売買の実務を想定しないと実行できなくなってしまいますので注意が必要です。
契約や売買代金の受領、買主への登記手続きは、遺言執行者が行ないますので、前述の通り、登記名義人が相続人であっても、その相続人は一切売却活動を行う必要はありません。
契約書の売主欄は 遺言執行者○○○○ とします。
④ 譲渡所得税など税務の注意
不動産売却による利益が出た場合、譲渡所得税の課税対象となり得ます。清算型遺言では売却代金の受取りが受遺者となりますが、実務上は一旦相続人名義で登記・売却されるため、課税名義・負担者の確認と整理が必要です。気を付けないと、不動産売却代金を相続しない相続人に譲渡所得税が課されたり、翌年の社会保険料が増えてしまう可能性があります。
⑤ 寄付・遺贈先との実務上の合意
「不動産を売ってその代金を寄付する」としても、実際にその寄付先(自治体・NPO法人・公益法人等)が不動産の受け入れ可否・寄付形態をどう考えているか事前確認しておくことが重要です。不動産本体の寄付は断られるケースもあります。
また、寄付先が「いつ売却するか」「売却後いつ寄付金が確定するか」「売却代金の変動による寄付額の増減があるか」などの点についても、遺言作成時(生前)に関係者で調整しておくことが望ましいです。
⑥ 遺言書の文言・形式・証人・保管
遺言自体が無効になってしまっては意味がありません。清算型遺言では特に複雑な売却・分配の流れがあるため、遺言書の文言を明確に、「何を売却する」「どのように売却代金を取り扱う」「差引の対象(債務、税金、費用等)」「残金の支払対象者」などを詳細に書いておくことが推奨されます。
例) 売却代金から税金・登記費用・遺言執行者報酬などを差し引いた残金を〇〇に遺贈する
また、形式(自筆証書遺言/公正証書遺言)や保管、遺言執行者の承諾取得、証人選任など相続・遺言法制の一般ルールも押さえておく必要があります。
不動産売却に関する遺言執行の流れ
- 生前遺言者が遺言書を作成
不動産特定・売却指示・遺贈対象団体明記・遺言執行者指定
- ステップ1被相続人死亡
相続開始(遺言執行者就任通知・財産目録作成 )
- ステップ2相続登記
遺言執行者が単独で被相続人から法定相続人名義への相続登記申請をする。
- ステップ3不動産売却
遺言執行者が単独で売買を行う。不動産仲介会社への査定依頼、媒介契約、売買契約、測量などの付随業務
- ステップ4売買代金受領
遺言執行者が売買代金を受領、仲介手数料などの費用を支払う
- ステップ5税務申告(譲渡所得税、相続税)
実務上仮に登記した相続人に課税されないように注意
- ステップ6遺贈先へ送金
売却費用・債務・税金等を精算して、残金を遺贈先へ交付
- ステップ7遺言執行完了
相続人へ報告等
おひとり様が安心して「清算型遺言」を活用するために
おひとり様が所有不動産を売却して寄付・遺贈する清算型遺言は、管理負担の軽減・公平な分配・明確な意思表明という点で有効な選択肢です。
ただし、実効性を確保するためには以下が鍵となります。
✅遺言執行者を指定しておくこと
✅不動産売却可能性・換価時期・費用・税金を事前に検討しておくこと
✅不動産売却に付随する業務を作成時に確認しておくこと(建物登記、測量、解体、通行掘削承諾など)
✅登記・名義変更の流れを理解しておくこと
✅税務上のリスクと負担所在を明確にしておくこと
✅寄付・遺贈先との実務調整を生前にしておくこと
✅遺言書の文言を明確にし、専門家の助言を得ること
これらを丁寧に検討・設計することで、遺言者が生前に抱いた「残したい意思」を死後も実現しやすくなります。特におひとり様の場合、相続人・受遺者・寄付先の協力が得づらいケースも想定されるため、遺言書の設計と作成を専門家と一緒に進めることを強くお勧めします。