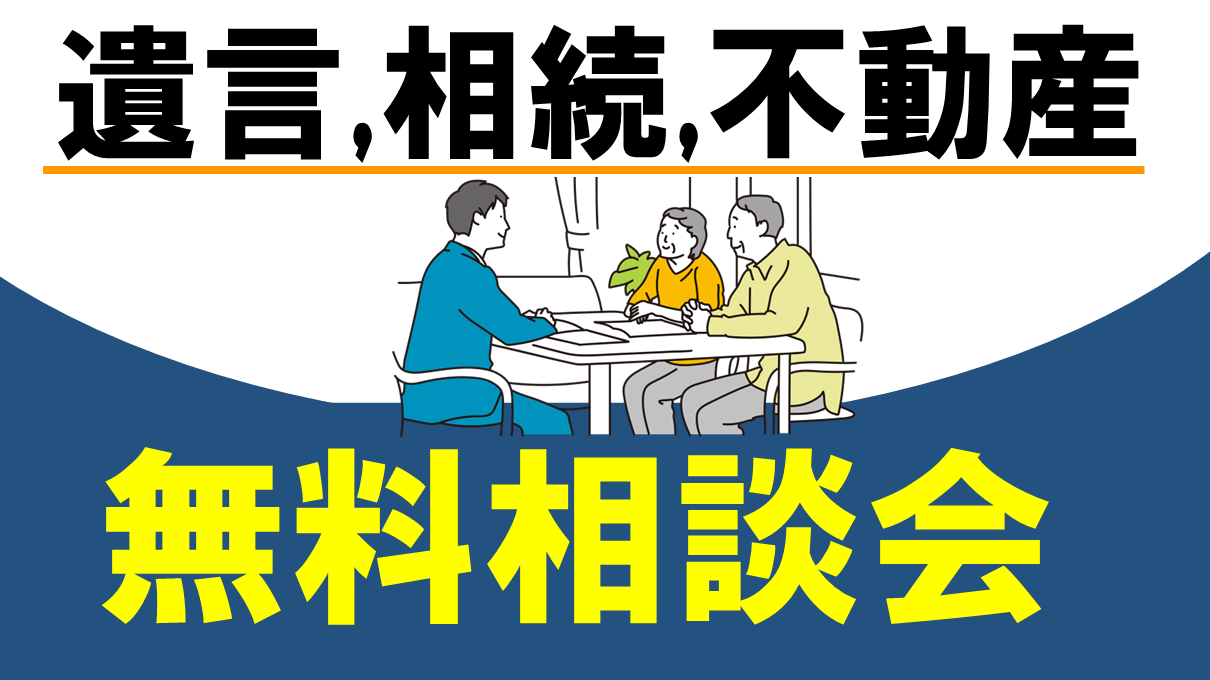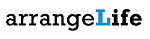今回は「事故物件を相続した場合、相続人はどのように対応すべきか?」について、不動産業と行政書士業を兼業する行政書士が法律と不動産の両面から解説します。
著者:行政書士 正木隆雄 埼玉県行政書士会朝霞支部(朝霞市、新座市、志木市、和光市)所属
遺言、相続、終活を専門とし、地域密着でシニアの暮らしの支援を行っています。
事故物件とは? 定義と現状を知る
事故物件とは、過去に自殺・殺人・孤独死・火災などが発生したことにより、心理的瑕疵(かし)がある物件のことを指します。
不動産取引においては、「告知義務」があるため、売却や賃貸の際に過去の事実を説明しなければならないケースがあります。
2021年、国土交通省より事故物件に関するガイドラインが出され、告知義務の範囲が明確になりましたが、それでもグレーな部分は残っており、慎重な対応が求められます。
相続登記は2024年から義務化。放置はNG
2024年4月から、相続登記が義務化されました。
正当な理由がなく、相続開始から3年以内に登記をしない場合、10万円以下の過料の対象になります。
売却?賃貸?それとも保有?事故物件の活用方法
事故物件は、一般的な物件と比べて価格が低くなる傾向にあります。
活用方法としては、以下の3つが考えられます:
- 売却:相場より2~5割程度安くなることも。買取専門業者に相談する選択肢もあります。
- 賃貸:価格を下げれば入居者がつくケースも。事故から時間が経てば心理的影響も薄れる傾向に。
- 保有・活用:更地にして売却、駐車場として貸すなどの活用も検討可能です。
不動産業者として、近隣相場や市場性を踏まえた最適な選択肢をご提案できます。
親族間トラブルを防ぐための文書化と話し合い
複数の相続人がいる場合、「誰が物件を取得するか」「売却して現金で分けるか」などをめぐって揉めるケースが少なくありません。
そこで重要になるのが、遺産分割協議書の作成です。
行政書士として、相続人全員の合意を確認し、法的に有効な書類を作成することで、後々のトラブルを未然に防ぐことが可能です。
専門家に相談することで得られる安心とスピード
事故物件の相続は、通常の相続よりも「心理的」「法的」「不動産的」なハードルが高いです。
当事務所では、以下のようなワンストップ対応が可能です:
- 相続手続きの相談・書類作成(行政書士)
- 事故物件の現地調査・査定・売却(不動産業)
- 特殊清掃・遺品整理業者の手配
- 必要に応じて司法書士・税理士との連携
まとめ
事故物件を相続すると、不安や迷いが生じやすいものです。
ですが、正しい知識と専門家のサポートがあれば、適切に対処し、納得のいく形で処理することができます。
「どうしたらいいか分からない」という段階でも、ぜひお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。